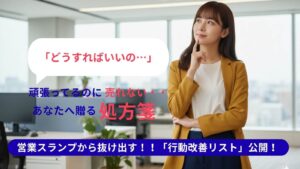その営業、「説明」で終わっていませんか?「物売り」時代の終焉と、顧客の未来を創るコンサルティング営業の本質
はじめに:なぜ、あなたの営業は「説明」で終わるのか?「物売り」時代の終焉と、求められる真の価値提供
「弊社のサービスはですね…」 「他社と比較して、このような優位性がありまして…」
もし、あなたの商談がこのような「説明」に終始しているとしたら。
残念ながら、あなたの営業活動は、すでに時代遅れになっている可能性が高いです。なぜなら、顧客は、もはやあなたの説明を必要としていないからです。
こんにちは。営業組織の戦略設計と人材育成を担っている筒井です。 インターネットが普及し、あらゆる情報が瞬時に手に入る現代において、営業担当者の役割は根本から変化しました。かつてのように、製品の機能やスペックを淀みなく説明するだけの「説明型営業」は、もはや通用しません。なぜなら、顧客は営業担当者に会う前に、Webサイトや比較サイト、SNSを通じて、あなたの商品について、あなた以上に詳しくなっているかもしれないからです。
にも関わらず、多くの営業現場では、いまだに古い成功体験に囚われ、「いかに上手く説明するか」「いかに多くの機能をアピールするか」といった、「物売り」の発想から抜け出せずにいます。その結果、「他社と比較検討します」「もう少し調べてみます」という、お決まりのセリフと共に、貴重な商談機会を失い続けているのではないでしょうか。
この記事は、そんな旧態依然とした「物売り営業」に終止符を打ち、現代の顧客から真に求められ、選ばれ続けるための新しい営業の在り方、すなわち「コンサルティング営業」の本質を、私の研修内容という一次情報に基づいて体系的に解説するものです。
単なる「課題解決」に留まらない、顧客自身も気づいていない「未来」を共に描き、その実現を支援する。それこそが、これからの時代に営業担当者が提供すべき、唯一無二の価値なのです。この記事を読み終える頃には、あなたがこれまで「営業」だと思っていたものの定義が覆り、明日からの行動を変えるための、明確な指針を手に入れているはずです。
第1章:時代遅れの「説明型営業」─ インターネットが変えた顧客と市場
なぜ、かつて有効だった「説明型営業」は、現代においてその価値を失ってしまったのでしょうか。その背景には、顧客を取り巻く環境の劇的な変化があります。
情報爆発と選択肢の増加:顧客は営業の説明を必要としなくなった
かつて、顧客が製品情報を得る手段は限られていました。営業担当者は、その希少な情報を持つ「情報の運び手」として、重要な役割を担っていたのです。製品のスペック、価格、導入事例…それらを丁寧に説明するだけで、顧客は価値を感じ、購買へと繋がりました。
しかし、インターネットの普及が全てを変えました。顧客は、PCやスマートフォン一つで、あらゆる情報を瞬時に比較検討できるようになったのです。公式サイト、レビューサイト、SNS、動画プラットフォーム…情報は爆発的に増加し、むしろ「情報過多」の中で、何を選べば良いのか分からない、という新たな課題に直面しています。
このような状況下で、営業担当者が一方的に製品の「説明」を繰り返しても、顧客にとっては「もう知っている情報」か、あるいは「情報が多すぎて処理しきれないノイズ」でしかないのです。
コモディティ化の波:商品単体での差別化は、もはや幻想
技術の進歩は、製品やサービスの同質化、いわゆる「コモディティ化」を加速させています。かつては画期的だった機能も、あっという間に競合に模倣され、価格競争に巻き込まれていきます。
「うちの製品は、他社よりも〇〇が優れています!」 そう力説したところで、顧客の心には響きません。「似たような話は、他の会社からも聞いた」「その程度の違いなら、安い方でいい」と思われてしまうのが関の山です。製品単体の機能やスペックだけで差別化を図り、顧客に選ばれ続けることは、極めて困難になっていると言えるでしょう。
「説明」だけで売れた時代の終焉
市場の変化は明らかです。顧客はより賢くなり、製品は同質化していきます。もはや、「説明が上手い」だけでは、営業として生き残れない時代なのです。顧客が営業担当者に求めているのは、カタログに載っているような情報の反復ではありません。彼らが本当に求めているのは、自社のビジネスが抱える複雑な課題を理解し、その解決策を共に考え、未来へと導いてくれる「羅針盤」のような存在なのです。
第2章:「物売り」から脱却せよ ─ 現代営業に求められる“コンサルティング”という役割
「説明型営業」が通用しないのであれば、我々は何を目指すべきでしょうか。多くの企業が「ソリューション営業」への移行を掲げますが、その実態は単なる「課題解決型営業」に留まっているケースが少なくありません。しかし、真に価値を提供するためには、もう一歩踏み込む必要があります。
ソリューション営業の誤解:「課題解決」だけでは足りない理由
「何かお困りごとはありますか?」 「その課題でしたら、弊社の〇〇で解決できます!」
いわゆるソリューション営業は、顧客の顕在的な課題(ニーズ)を聞き出し、それに対して自社の商品やサービスを当てはめていくアプローチです。これは「説明型営業」よりは一歩進んでいますが、まだ不十分と言えます。なぜなら、以下の2つの限界があるからです。
- 顧客自身が、本当の課題を認識していない可能性がある: 顧客が口にする「困りごと」は、氷山の一角に過ぎないことが多いのです。その表面的な課題に対応するだけでは、根本的な問題解決には至らず、顧客の満足度も限定的になります。
- 競合との差別化が難しい: 顕在的な課題に対しては、当然、競合他社も同様の解決策を提案してきます。結局は、価格や機能の比較競争に陥りやすくなります。
真の価値提供とは、単に顧客の「御用聞き」になることではありません。顧客自身もまだ気づいていない、より本質的な課題を発見し、その解決を通じて、顧客のビジネスを新たなステージへと引き上げることなのです。
目指すべきは「事業戦略のパートナー」
私が提唱するのは、「ソリューション営業」のさらに先、「コンサルティング営業」です。その定義は明確です。単なる「物売り」や「課題解決屋」ではなく、顧客の「事業戦略のパートナー」となること。
これは、単に商品を売ることではありません。顧客の現状と、彼らが目指すべき理想の未来を深く理解し、そのギャップを埋めるための戦略を共に描き出すことです。時には、顧客自身も気づいていない市場の機会や、潜在的なリスクを指摘し、新たな事業戦略そのものを提示することさえ求められます。
このレベルの関係性を築くことができて初めて、あなたは競合他社という土俵から抜け出し、顧客にとって「かけがえのない存在」となることができるのです。
「夢」を売るな、「実現可能な未来」を設計せよ
しばしば営業研修では「お客様に夢を見せろ」と語られます。しかし、ここで言う「夢」とは何か、その定義を誤ってはなりません。我々が見せるべきは、実現不可能な空想、いわば「寝ている時に見る夢」ではないのです。
コンサルティング営業が見せるべきは、顧客の事業ビジョンに基づいた、**具体的で、達成可能な「将来の夢」、すなわち「起きている時に見る夢」**です。
「このサービスを導入すれば、バラ色の未来が待っています!」といった、根拠のないオーバートークは、むしろ顧客の信頼を失います。重要なのは、顧客の現状を正確に把握し、理想の未来(ゴール)を設定した上で、そこに至るまでの**具体的なプロセス、すなわち「階段」**を、顧客と共に一段ずつ設計していくことなのです。
現状と理想を繋ぐ「階段」を架ける技術
顧客の多くは、「こうなりたい」という理想は持っていても、現状からそこへどうやってたどり着けば良いのか、その具体的な道筋(階段)が見えていないことがあります。あるいは、その階段の途中に、自分では気づいていない「穴」が開いていることさえあるのです。
コンサルティング営業の役割は、この壊れた階段を修復し、顧客が安心して一歩ずつ登っていけるように、道筋を照らしてあげることです。
- 現状分析: 顧客のビジネスモデル、市場環境、競合状況、組織体制などを徹底的にヒアリングし、現状を正確に把握します。
- 理想の定義: 顧客が目指す「将来の夢」を具体的に言語化し、共有します。
- ギャップ特定: 現状と理想の間にある「ギャップ」こそが、解決すべき問題点であることを明確にします。
- 原因分析: なぜ、そのギャップが生まれているのか、根本原因を顧客と共に深掘りします。
- 戦略策定: 根本原因を取り除くための具体的な戦略(階段)を設計します。
- 実行支援: 設計した戦略を実行するための最適なツールとして、自社のサービスを位置づけ、導入から成果創出まで伴走します。
この「階段を架ける技術」こそが、単なる物売りとコンサルティング営業を分ける、決定的な違いとなります。
第3章:核心スキル① ─ 顧客自身も気づいていない「本質的な課題」を発見する力
コンサルティング営業の成否は、いかに顧客の「本質的な課題」を発見できるかにかかっています。これは、単にヒアリングシートを埋める作業ではありません。深い洞察力と分析力が求められる、極めて知的なプロセスです。
ヒアリングの罠:表面的な課題に飛びついていませんか?
多くの営業は、顧客が最初に口にした「困りごと」に飛びつき、すぐに自社の商品説明を始めてしまいがちです。しかし、それは多くの場合、症状に過ぎません。例えば、「新規顧客が獲得できない」という悩み。これは症状であり、その裏には「市場の変化に対応できていない」「競合と比較して自社の魅力が伝わっていない」「そもそもターゲット設定が間違っている」といった、より根深い原因(病巣)が隠れている可能性があります。
表面的な症状に対して対症療法(例:広告を増やす)を施しても、根本原因が解決されなければ、問題は再発します。コンサルティング営業は、この根本原因、すなわち**真の“イシュー”**にまでメスを入れる必要があります。
「なぜ?」の先へ:ギャップ分析を深化させる
本質的な課題を発見するための基本は、「なぜ?」を繰り返すことです。しかし、単に「なぜですか?」と問い続けるだけでは、顧客を詰問しているように聞こえかねません。重要なのは、顧客のビジネス全体を構造的に理解した上で、「なぜ?」を戦略的に投げかけることです。
- 現状(As Is): 現在の具体的な状況、指標、取り組みはどうなっていますか?
- 理想(To Be): 本来あるべき姿、目指している目標は何ですか?
- ギャップ(Gap): 現状と理想の間にある具体的な差分は何でしょうか?
- 原因(Cause): なぜ、そのギャップが生まれているのでしょうか?(内的要因・外的要因)
- 影響(Impact): そのギャップを放置すると、どのような悪影響がありますか?逆に、解決すればどのような好影響が期待できますか?
このフレームワーク(私の研修ではGAPSSモデルとして教えています)に沿ってヒアリングを進めることで、対話は自然と深掘りされ、表面的な悩みから本質的な課題へと焦点が絞られていきます。
真の“イシュー”を見極める洞察力
本質的な課題(イシュー)とは、それを解決すれば、顧客のビジネス全体に最も大きなインパクトを与えられる「一点」のことです。数ある課題の中から、この最重要課題を見極める洞察力が、コンサルティング営業には不可欠です。
そのためには、顧客の業界動向、ビジネスモデル、収益構造、組織文化といった、よりマクロな視点での理解が求められます。顧客以上に顧客のビジネスに精通し、彼らがまだ気づいていない機会や脅威を示唆できるレベルを目指さなければなりません。
AI時代に営業が生き残る道:「問題発見」という人間だけの価値
近年、AIの進化は目覚ましいものがあります。製品情報の提供や、単純な課題解決策の提示であれば、AIの方が人間よりも速く、正確かもしれません。しかし、AIにはできないことがあります。それが**「問題発見」**です。
顧客の言葉のニュアンス、表情の変化、組織内の力学…そうした非言語的で複雑な情報の中から、真の課題を発見する。これは、人間にしかできない高度な知的作業です。AIを単なる脅威と捉えるのではなく、AIにはできない「問題発見」と「戦略設計」にこそ、営業担当者の存在価値があります。この認識を持つことが、これからの時代を生き抜く鍵となるでしょう。
第4章:核心スキル② ─ 「あなたから買う理由」を創造する価値提案(バリュープロポジション)
本質的な課題を発見できたとしても、それだけでは受注には繋がりません。「なぜ、その課題を“あなたの会社”のサービスで解決する必要があるのか?」という問いに、明確に答える必要があります。それが、**独自の価値提案、すなわち「バリュープロポジション」**の構築です。
「良いサービス」だけでは選ばれない現実
コモディティ化が進む現代において、「良いサービスです」「高品質です」といった漠然としたアピールは、もはや意味をなしません。顧客は常に「他社と何が違うのか?」「自分にとって、具体的にどんなメリットがあるのか?」という比較の視点を持っています。
あなたの提案が、数ある選択肢の一つとして埋もれてしまわないためには、「あなただけの独自の価値」を明確に定義し、顧客に伝えきる必要があるのです。
バリュープロポジションとは何か?
バリュープロポジションとは、**「顧客(エンドユーザー)が抱える特定の課題に対して、自社(顧客企業)が独自の強みを生かして、どのように解決できるか。そして、それによってどのような具体的な成果(価値)を提供できるのか」**を明確にした、顧客への約束のことです。
単なる自社の「強み(USP)」とは異なります。USPが自社視点であるのに対し、バリュープロポジションは**「市場(顧客)から見て、どのような価値があるか」**という視点で定義されます。市場が求めていない強みは、価値にはなり得ません。
顧客(エンドユーザー)×自社(顧客企業)×競合 = 独自の価値
強力なバリュープロポジションは、以下の3つの要素の重なりから生まれます。
- 顧客(エンドユーザー)は何を求めているか?: 顧客が本当に解決したい課題、満たしたい欲求は何か?(市場のニーズ)
- 自社(顧客企業)は何を提供できるか?: そのニーズに対して、自社独自の強み、リソース、ノウハウで何ができるか?(自社のケイパビリティ)
- 競合は何を提供できないか?(あるいは、自社の方が優れている点は何か?): 同じニーズに対して、競合他社にはない、自社だけのユニークな価値は何か?(競合優位性)
この3つの円が重なる部分こそが、あなたの会社が提供すべき独自の価値であり、顧客が「あなたから買う理由」となるのです。
戦うべき市場を見極め、定義する戦略眼
バリュープロポジションを構築することは、同時に**「戦うべき市場(土俵)」**を定義することでもあります。多くの企業は、自社の強みを活かせない、競合ひしめくレッドオーシャンで無駄な戦いを挑み、疲弊しています。
例えば、水漏れ修理の会社が「最短30分で駆けつけます!」とアピールしても、大手企業が「15分で駆けつけます」と謳っていれば、勝ち目はないでしょう。その場合、「速さ」という土俵で戦うべきではないのです。「価格」で勝負するのか、「深夜対応」で勝負するのか、あるいは「特定の地域に特化」することで、大手にはない価値を提供するのか。
コンサルティング営業は、顧客企業の強みと市場環境を冷静に分析し、彼らが本当に勝てる土俵を見つけ出し、そこで戦うための戦略(バリュープロポジション)を共に構築する役割を担います。
第5章:【実践録】コンサルティング営業は、こうして価値を生む
理論だけでは不十分です。ここでは、私の研修で共有している実際の成功事例を通じて、コンサルティング営業がどのように価値を生み出すのかを具体的に見ていきましょう。
事例1:単なるSNS運用ではない、「事業戦略」としての提案(福利厚生企業の事例)
SNSコンサルティング会社に対する福利厚生サービスの提案事例です。当初、顧客はSNS集客に成功しており、福利厚生にもWebマーケティングにも関心が薄い状態でした。まさに「物売り」では手も足も出ない状況です。
しかし、担当者は商材の話を一旦止め、顧客の事業展望に焦点を当てました。ヒアリングを深める中で、「10年以内に上場したい」という顧客の**「将来の夢(起きている夢)」**が明らかになりました。
そこから逆算し、「上場のためには、SNSだけでなく、Webサイトを通じた信頼性向上とリード獲得が不可欠である(新しい階段の提示)」、「しかし、顧客にはコンテンツ作成のリソースがない(階段の穴)」 という本質的な課題を特定。最終的に、「WebサイトのSEO対策+コンテンツ作成代行(リソース提供)」という、当初の福利厚生とは全く異なる価値提案で受注に至りました。これは、顧客の事業戦略パートナーとして、新たな価値を創造した典型例と言えます。
事例2:「アート思考」の“本当の価値”を再定義する(研修コンサルタントの事例)
大手企業との取引が中心で、新規集客に困っていない研修コンサルタントの事例です。彼らが提供するのは「アート思考」という、まだ一般には認知度の低い思考法でした。
ここでも、単なる集客支援の提案は響きません。担当者は、顧客の**「アート思考を、もっと世の中に普及させたい」という理念(理想)**に着目しました。そして、「その理念を実現するためには、大手だけでなく、むしろ課題を抱える中小企業にこそ、アート思考を届けるべきではないか?」という新たな視点を提示したのです。
しかし、「アート思考なんて誰も知らないから、中小企業には売れないだろう」という顧客の**思い込み(前提)**がありました。そこで担当者は、「アート思考そのものを売るのではなく、『中小企業の漠然とした悩みを解決する』という価値を前面に出し、その具体的な手法がたまたまアート思考だった、という見せ方(バリュープロポジションの再定義)をすればいい」と提案しました。この提案が顧客の心を掴み、受注に繋がったのです。
事例3:不動産屋に「不動産屋をやめさせる」という価値創造(不動産会社の事例)
集客に苦しみ、強みもない地方の不動産会社の事例です。ボランティア程度にFP(ファイナンシャルプランナー)相談も行っていました。
担当者は、「不動産市場では、御社に勝ち目はない(戦うべき市場の誤り)」と正直に指摘しました。その上で、「競合のいないFP相談を事業の軸に据え、まずはお金の相談相手として顧客との信頼関係を構築し、最終的に不動産売買に繋げる、という新しいビジネスモデル(事業戦略の転換)を構築してはどうか?」と提案したのです。
これは、もはや単なるWeb集客の提案ではありません。顧客の事業そのものを再定義し、新たな価値を創造する、究極のコンサルティング営業と言えるでしょう。
第6章:思考を加速させる武器 ─ テクノロジー(AI)との向き合い方
コンサルティング営業には、深い思考力が求められます。その思考を加速させ、より精度の高い仮説を構築するために、テクノロジー、特にAIをいかに活用するかも重要なテーマとなります。
AIは「壁打ち相手」:予習と仮説構築を加速させる
私の研修では、商談前の予習を効率化・深化させるためのAIツールを紹介しています。顧客のWebサイトURLや業種、過去の商談履歴などをインプットすることで、AIは競合調査、市場分析、想定される課題の洗い出しなどを瞬時に行ってくれます。
これは、営業担当者がゼロから情報を収集・分析する手間を大幅に削減し、より本質的な「仮説構築」に時間を集中させるための、強力な武器となります。AIを「壁打ち相手」として活用し、様々な角度から質問を投げかけることで、自分だけでは思いつかなかった新たな視点や戦略のヒントを得ることも可能です。
限界を知る:AIは解決策は出せても、問題は発見できない
しかし、AIは万能ではありません。AIは、与えられた情報に基づいて、最適な「解決策」を提示することは得意ですが、「そもそも解決すべき問題は何か?」を発見することはできないのです。
顧客の真の課題を発見するためには、言葉の裏にある感情を読み取り、複雑な人間関係を理解し、時には直感を働かせるといった、人間ならではの高度な能力が不可欠です。AIの分析結果を鵜呑みにするのではなく、それをあくまで一つの参考情報として、最終的な判断は自身の思考力で行わなければなりません。
未来の営業に求められる、AIを使いこなすための「思考力」
これからの営業担当者に求められるのは、AIに代替されるような単純作業ではなく、AIを**「使いこなす」**ための思考力です。
- AIに的確な指示を与えるための「質問力」
- AIが導き出した答えを鵜呑みにしない「批判的思考力」
- AIでは発見できない本質的な課題を見抜く「洞察力」
- AIには生み出せない、創造的な解決策を発想する「戦略的思考力」
AIの進化を恐れる必要はありません。むしろ、AIを最強の「副操縦士」として使いこなし、人間であるあなたにしかできない「価値創造」に集中すること。それこそが、未来の営業の姿なのです。
まとめ:説明をやめ、思考せよ。コンサルティング営業こそが、未来を切り拓く唯一の道
時代は変わりました。かつての「説明型営業」「物売り営業」は、もはや過去の遺物です。顧客が真に求めているのは、単なる商品情報ではなく、自社の未来を共に描き、その実現を支援してくれる**「事業戦略のパートナー」**なのです。
そのためには、あなた自身が変革しなければなりません。
- 役割の再定義: 「物売り」から「コンサルティング営業」へ。顧客の課題解決ではなく、事業成功にコミットすることが求められます。
- スキルの進化: 「説明力」から「課題発見力」と「価値提案力(バリュープロポジション構築力)」へ。顧客も気づいていない本質を見抜き、独自の価値を創造する必要があります。
- 思考の深化: 「How(どう売るか)」から「Why(なぜ顧客は買うべきか)」「What(顧客が本当に得る価値は何か)」へ。表面的な事象にとらわれず、本質を思考し続けることが重要です。
これは、決して容易な道ではありません。常に学び続け、思考し続け、自身をアップデートし続ける覚悟が求められます。しかし、このコンサルティング営業という道を極めることができれば、あなたは単なる「営業担当者」という枠を超え、市場価値の高い「ビジネスプロフェッショナル」として、どんな時代でも必要とされる存在になれるはずです。
説明することをやめ、思考することを始めましょう。それこそが、あなたの、そして顧客の未来を切り拓く、唯一の道なのですから。
1400名規模のITベンチャー企業の営業部長・現ストラテジスト。
これまでに300名以上の営業マンの育成や営業組織の設計に携わり、商談スクリプトの構築や各業界のトップセールスの営業スキルの暗黙知を形式知にするなどの教育メソッドを体系化。
営業を「属人的な才能」ではなく「再現できる仕組み」として確立することを専門領域としている。
本サイトでは、営業力を高めたい個人や、営業教育を仕組み化したい法人に向けて、現場で成果を出すためのノウハウと知見を発信している。