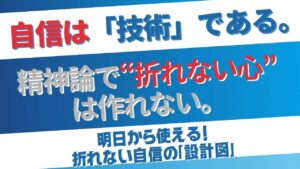【私の失敗談】営業ヒアリングで「それじゃない感」を出された私が、トップセールスに変われた理由
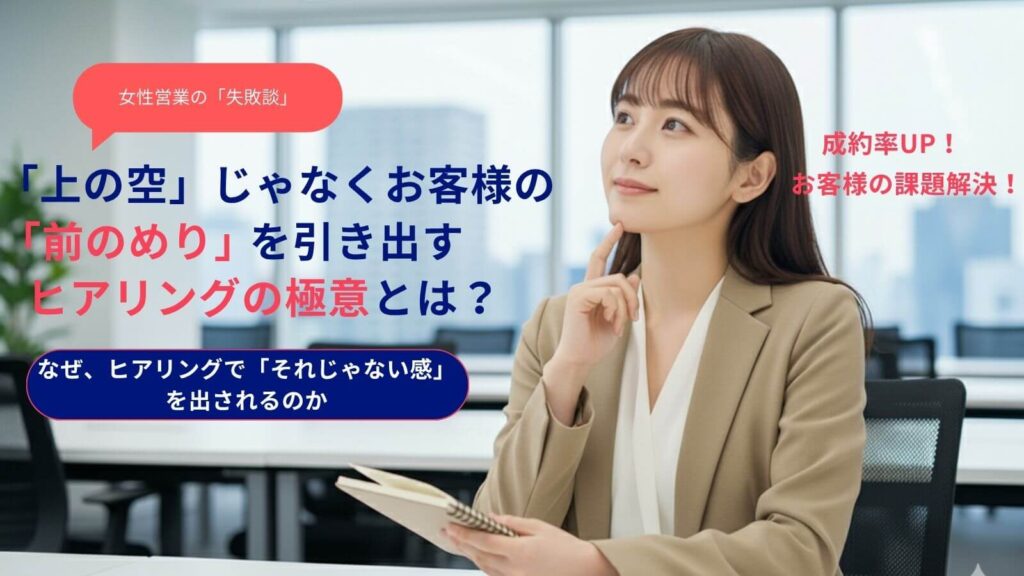
はじめに:完璧なプレゼンのはずが、「検討します」で終わっていたあの頃
「弊社が提供するSaaSツール『〇〇』は、最新のAI技術を搭載しており、競合のA社やB社と比較しても、これだけの優位性があります。導入実績も…」
完璧なプレゼンテーションのはずでした。お客様の課題も事前に調べ、想定される質問への回答も用意し、自信を持って臨んだ商談。しかし、お客様の反応は、どこか上の空。そして、最後に告げられたのは、いつものあの言葉でした。
「なるほど、よく分かりました。ありがとうございます。一度、持ち帰って検討させてください」
こんにちは、美咲詩乃です。
今でこそ、お客様から「美咲さんに相談してよかった」と言っていただけるようになりましたが、SaaSサービスの営業をしていた頃の私は、まさに冒頭のような失敗を繰り返していました。
競合も多く、情報が溢れかえるこの時代に、ただ商品の機能やスペックを説明する「もの売り営業」では、もうお客様の心は動きません。頭では分かっているつもりでも、どうすればいいのか分からず、私は完全に道を見失っていました。
そんなドン底の私を救ってくれたのが、このサイトの監修者でもある、当時の上司・筒井さんから教わった、ある「ヒアリングの哲学」でした。
この記事は、単なるヒアリングのテクニック集ではありません。 「もの売り」だった私が、お客様も気づいていない課題を引き出し、その解決策を売る「コンサルティング営業」へと生まれ変わるまでの、苦悩と試行錯誤の全記録です。
もしあなたが、私と同じように「一生懸命説明しているのに、なぜかお客様に響かない」と感じているなら、この記事が、あなたの営業人生を変えるきっかけになるかもしれません。
第1章:「もの売り営業」の限界。良かれと思って話すほど、お客様は離れていく
売れない時期の私は、とにかく「話す」ことに必死でした。自社サービスの優れた点を、一つでも多く、少しでも分かりやすく伝えなければ。その一心で、商談時間の8割を自分のプレゼンテーションに費やしていました。
ヒアリングも、もちろんしていました。しかし、今思えばあれはヒアリングとは呼べない、**自社の商品を売り込むための「粗探し」**のようなものだったのです。
(当時の私の、典型的なヒアリング)
私: 「現在、何かお困りごとはございますか?」
お客様: 「うーん、新規顧客の獲得が少し伸び悩んでいてね…」
私: 「(待ってました!)それでしたら、弊社の『〇〇』にお任せください! まさに、そういった新規顧客の獲得を得意とするツールなんです!具体的には…」
お客様が口にした表面的な課題に、食い気味に飛びつく。そして、そこから延々と自社製品のプレゼンテーションを繰り広げる。良かれと思ってやっていました。お客様の課題に、最速で解決策を提示しているつもりでした。
しかし、お客様の反応はいつも同じ。「なるほど」「すごいですね」と相槌は打ってくれるものの、その目は全く笑っていません。明らかに「君が言いたいことは分かったから、もういいよ」という空気が流れているのです。そして商談の最後には、「素晴らしいツールですね。ただ、うちにはまだ早いかもしれないので、一度持ち帰って検討します」という、丁寧な「お断りの言葉」が返ってくるだけでした。
そしてある商談で、ついに、お客様から核心を突く一言を言われてしまったのです。
「美咲さん、君の言っていることはよく分かった。ツールが素晴らしいのも分かった。でもね、君は、うちが“なぜ”新規顧客を獲得できずにいるのか、その本当の理由を、たぶん理解していないよね?」
衝撃でした。 私はお客様を見ていませんでした。見ていたのは、自社のサービスが解決できる「課題」という名の記号だけ。お客様がこれまでどんな努力をしてきたのか、どんな組織的な問題を抱えているのか、その背景にある複雑な事情には一切目を向けず、ただ「自社のツールを当てはめること」しか考えていなかったのです。
この「顧客不在」の営業スタイルこそが、お客様に「この人は、私たちのことを何も分かってくれていない」という決定的な不信感を与えていたのです。
第2章:筒井さんから伝授された「未来への地図」
その日の夕方、私は藁にもすがる思いで、筒井さんに相談しました。お客様から言われた言葉、自分の営業スタイルの限界、全てを正直に話しました。
私の話を黙って聞いていた筒井さんは、静かにこう言いました。
「美咲さんはヒアリングを『情報収集』だと思っているから、そうなるんだよ。本当のヒアリングとは、『お客様と共に、未来への地図を描く共同作業』のことだよ」
そう言って彼が見せてくれたのが、彼が研修で教えている独自のヒアリングフレームワークの資料でした。
このフレームワークの理論的な背景や詳細については、筒井さん自身が執筆したこちらの記事で、より深く学ぶことができます。
👉 【SPIN話法の上位互換】トップセールスの「ヒアリング」を完全再現するGAPSSモデルとは?
その資料に書かれていた「GAPSS(ギャップス)モデル」は、私にとって革命でした。
- G (Gap): お客様の「理想」と「現状」を特定し、そのギャップを明確にする。
- A (Analysis): なぜそのギャップが生まれているのか、根本原因を分析する。
- P (Problem): 原因を解決するために、今取り組むべき課題を定義する。
- S (Solution): 課題を解決する解決策として、自社サービスを位置付ける。
- S (Success): 解決策によって、当初の理想が実現できるという成功イメージを共有する。
私がやっていたのは、最初の「G」の段階で表面的な課題を聞き、すぐに「S(解決策)」に飛びつくという、最もやってはいけないことでした。お客様が最も納得感を得るために不可欠な、**「A(原因分析)」と「P(課題設定)」**という、最も重要なプロセスが、私のヒアリングからは完全に抜け落ちていたのです。
これは単なる質問の順番ではありませんでした。お客様自身も気づいていない問題の本質を共に発見し、その解決までの道のりを一緒に描いていく、コンサルタントそのもののアプローチでした。
第3章:「知っている」から「できる」への、泥臭い反復練習
理論は分かりました。しかし、実践は全くの別物でした。
頭ではGAPSSモデルを理解していても、いざお客様を目の前にすると、焦りからいつもの「もの売り」の自分に戻ってしまう。ヒアリングシートをただ埋めるだけの、尋問のようなぎこちない会話になってしまう。
「頭では理解できるんです。でも、お客様を目の前にすると、どの質問をすればいいか分からなくなって…」
そんな私に、筒井さんは「当たり前だ」と言い、一つの課題を出しました。それは、「毎日、1時間のロープレ」でした。
筒井さんがお客様役となり、様々な業界、様々な性格の担当者を演じ、私にGAPSSモデルを使ったヒアリングを何度も何度も繰り返させたのです。
DISC理論に基づいた、4タイプの顧客シミュレーション
筒井さんは、ただお客様役をやるだけではありませんでした。人の行動傾向を4つに分類する**「DISC理論」**に基づき、毎日違うタイプの顧客を演じ分けたのです。
- Dタイプ(主導型)の社長役:
筒井さん(D役):「前置きはいいから、結論から話して。このツールで、うちの売上は具体的にいくら上がるんだ?」 私(当時):「は、はい!ええと、まず現状の課題としましては…」 筒井さん(D役):「違う。俺が聞きたいのは未来の話だ。君のヒアリングはまだるっこしい」 - iタイプ(感化型)の担当者役:
筒井さん(i役):「いやー、美咲さん、この前の週末、ゴルフに行ってさー!スコアがね…」 私(当時):「(すごい雑談が長引く…どうやって本題に戻そう…)は、はは…すごいですね…」 - Sタイプ(安定型)の担当者役:
筒井さん(S役):「新しいツールを入れるのは、現場が混乱しそうで不安ですね…。今まで、導入して失敗した企業さんはないんですか?」 私(当時):「だ、大丈夫です!サポート体制は万全ですので!」(←具体的な根拠を示せず、ただ安心させようとして失敗) - Cタイプ(慎重型)の担当者役:
筒井さん(C役):「その『顧客エンゲージメントが向上する』というデータですが、根拠は何ですか?どういう計算式で算出された数値なのか、詳細な資料をいただけますか?」 私(当時):「(そ、そこまで細かく聞かれるとは…)も、持ち帰って確認します…」
このロープレを通じて、私は「誰にでも同じヒアリングが通用するわけではない」ということを、骨身に染みて理解しました。
Dタイプの社長には、まず「Success(成功)」のイメージを共有してから逆算してヒアリングを進める。Sタイプの担当者には、「Solution(解決策)」の導入事例を丁寧に説明し、不安を取り除く時間を長く取る。
この泥臭い反復練習を数ヶ月続けた結果、私のヒアリングは、徐々に血の通った「対話」へと変わっていきました。
【サイト内リンク:筒井氏の解説記事】 DISC理論と、それに基づいた信頼関係の構築方法については、こちらの筒井さんの記事が非常に参考になります。
👉
第4章:あの日、あの瞬間。ヒアリングが「武器」に変わった
ロープレを始めて3ヶ月が経った頃。あるIT企業の部長様との商談で、私にとっての決定的な「ブレークスルーの瞬間」が訪れました。
その企業は、優秀なエンジニアを採用できずに困っていました。いつもの私なら、すぐに自社の採用支援サービスの話を始めていたでしょう。しかし、その日の私は違いました。筒井さんと繰り返したロープレの通り、GAPSSモデルの「A(原因分析)」を徹底的に深掘りしたのです。
私: 「色々な施策を試されているのに、なぜ採用がうまくいかないのでしょう…?」
部長様: 「うーん、結局は知名度と待遇で、大手企業に負けてしまうんですよ」
私: 「なるほど…。ただ、先ほど『御社のエンジニアの方は、技術レベルが非常に高く、仕事も面白い』とおっしゃっていましたよね。その魅力が、なぜか候補者の方に伝わっていない。その**『伝達のボトルネック』は、どこにあると思われますか?」
部長様: 「…それは、うちの現場エンジニアが、採用活動に非協力的だからかもしれない。彼らは自分の仕事にプライドを持っているけど、それを外部にアピールするのは苦手なんだ」
私: 「ということは、御社の本当の課題は、『優秀な人材が採用市場にいない』ことではなく、『社内にある最高の魅力を、採用候補者に届けるための“翻訳者”がいない』ことそのものにある、とは言えないでしょうか?」
その瞬間、部長様は、ハッとした表情で、しばらく黙り込みました。そして、「美咲さん、その通りかもしれない…。私たちは、外にばかり目を向けて、自分たちの足元にある宝物を磨く努力を怠っていた」と呟いたのです。
この時、私の全身を駆け巡った、得も言えぬ高揚感を、今でも忘れることができません。 それは、商品を売れた時の喜びとは全く違う種類の感情でした。お客様が今まで気づいていなかった問題の本質を、私の質問によって引き出し、その瞬間に、お客様の目の色が「営業を受ける側」から「共に課題解決に取り組むパートナー」へと変わったのが、肌で感じられたのです。
商品を売ったわけでも、契約を取ったわけでもない。ただ、お客様自身も気づいていなかった問題の本質を、ヒアリングを通じて言語化し、「気づき」を与えられた。その瞬間に得られた、お客様からの深い共感と信頼。
この時、私は確信しました。 ヒアリングとは、単に情報を「聞く技術」ではない。お客様に、新たな視点という「気づきを与える技術」なのだ、と。
この日を境に、私は「もの売り営業」を完全に卒業し、お客様の課題を共に発見し、解決する「コンサルティング営業」へと生まれ変わったのです。
まとめ:あなたのヒアリングは、明日から「武器」になる
私の失敗談と、そこからの長い道のりにお付き合いいただき、ありがとうございました。
もし、かつての私と同じように、「もの売り」の限界を感じているなら、ぜひ筒井さんの提唱する「GAPSSモデル」を学んでみてください。そして、ただ学ぶだけでなく、
- GAPSSモデルに基づいた、自分だけのヒアリングシートを作ってみる。
- 同僚や上司にお願いして、徹底的にロープレを繰り返す。
この泥臭い実践の先にしか、本当の進化はありません。
ヒアリングは、もはや情報収集のツールではありません。それは、お客様の未来を共に描き、深い信頼関係を築くための、営業における最強の「武器」なのです。
あなたのヒアリングが、明日から少しでも変わることを、心から願っています。

元営業ウーマン。現在28歳。
新人時代には数字に追われて悩み、営業を辞めたいと思った経験もあるが、学びを通じて成果を伸ばし、営業の面白さに気づいた。
今は「営業をもっと楽しく、長く続けられる仕事に」という想いから、読者に寄り添った記事を執筆。
本サイトでは、営業現場でのリアルな悩みや体験談を交えながら、共感型のコンテンツを発信している。